ホームヘルパーとは
訪問介護員(ホームヘルパー)とは、心身に障害がある方や高齢者などの家庭を訪問して、家事援助や介護をする人のことで、各都道府県知事が1級~3級課程の研修を指定しています。
介護保険制度が施行され、実際に介護の現場でサービスを提供するホームヘルパーは、いま最も必要とされる人材で、皆様の生活をお手伝いする大切なお仕事ですから資格が必要となります。
ホームヘルパーと歯科衛生士
 歯科衛生士の養成所(短期大学・専門学校)では従来2年間の教育課程でしたが、現在では3年間(4年間の場合もある)に移行しています。
歯科衛生士の養成所(短期大学・専門学校)では従来2年間の教育課程でしたが、現在では3年間(4年間の場合もある)に移行しています。
ホームヘルパーも人材不足といわれていますが、これは歯科衛生士の資格を有するものが歯科の訪問介護を含めホームヘルパーとしての資格をもって活躍することが期待されているからなのです。
それではホームヘルパーについて概略を紹介させていただきます。
ホームヘルパーの資格
ホームヘルパーの資格は1級から3級までの3種類に分かれ、看護師や准看護師、介護福祉士などの資格を保有する者がヘルパーとして勤務するときはホームヘルパー1級の資格に準ずるものとされます。
ホームヘルパーの資格は全国で有効になります。
- 3級 受講資格なし 講義、実習時間50時間
- 介護保険制度の上では、ホームヘルパーとして働くことができますが、多くの企業や施設などの現場では2級以上を求めています。家事援助のみのサービス提供ができます。
- 2級 受講資格なし 講義、実習時間130時間
- 試験等はありませんが、3日間の実習が義務付けられています。
ヘルパー資格の多くの募集において2級以上が必要とされます。訪問介護の実務者として生活支援・身体介護・相談助言を行なうことができます。
- 1級 受講資格2級ヘルパーとして1年以上の実務経験 講義、実習時間230時間
- ヘルパーとしての充分な知識経験や高度な技術のほか、他の
ヘルパーをとりまとめる中心的な役割を担います。施設の主任ヘルパーといったサービス責任者としても活躍の場が広がっています。
ホームヘルパーの資格取得
ホームヘルパーの資格を取るためには、都道府県の指定養成講座(養成研修)を修了しなくてはなりません。
養成研修は、各市町村及び各市町村社会福祉協議会、農業協同組合、生活協同組合、専門学校、民間企業などで実施しています。
=参考=
介護保険法第7条(定義)
6 この法律において「訪問介護」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)であって、居宅(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(第16項において単に「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者等」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
介護の現場では、ホームヘルパーとして働くためには2級以上の資格が求められるため、2級以上の養成講座を受講されると良いでしょう。
ホームヘルパーの指定養成講座
養成講座には通学課程に加えて、通信課程を設けているところもあります。ご自分のライフスタイルに合わせた選択が可能のようです。
ただし、ホームヘルパーの業務には重いものを運ぶこともありますので、腰痛など身体的な負担に耐えられないと思われる場合など受講できないことがあります。
一般的に、年齢・性別・学歴・国籍などの条件はありません。
今後新たに資格取得をお考えの方は、下記教育訓練給付制度をご活用されてはいかがでしょうか。
教育訓練給付制度
主体的な労働者の能力開発や取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の新しい給付制度です。厚生労働大臣の指定する講座(本講座)を受講したものに対して、公共職業安定所が受講に要した費用の4割を助成するものです。
支給対象の方は全過程修了後、5年以上雇用保険に加入の方は基本受講料の4割が公共職業安定所より支給され、3年以上雇用保険に加入の方は基本受講料の2割が支給されます。
例えば、次の表のような感じになります。
- 通常料金
- 通学課程 : 80,000円 / 通信課程 : 70,000円
- 5年以上加入(4割助成)
- 通学課程 : 48,000円 / 通信課程 : 42,000円
- 3年以上加入(2割助成)
- 通学課程 : 64,000円 / 通信課程 : 56,000円
対象者は通算して3年以上雇用保険に入っている方(パート可)
(3年以上~5年未満の方は2割給付、5年以上の方は4割給付となります)
現在お仕事をされてない方でも、退職されてから1年以内で雇用保険に3年以上入っていた方(転職などがあった場合は、その間が1年未満であれば可能)。
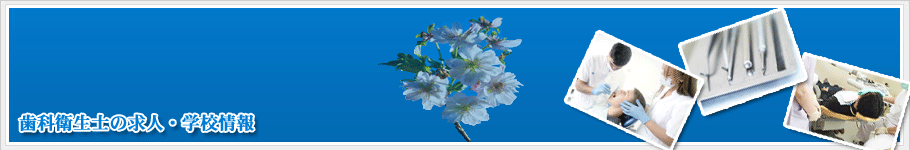





 歯科衛生士の養成所(短期大学・専門学校)では従来2年間の教育課程でしたが、現在では3年間(4年間の場合もある)に移行しています。
歯科衛生士の養成所(短期大学・専門学校)では従来2年間の教育課程でしたが、現在では3年間(4年間の場合もある)に移行しています。